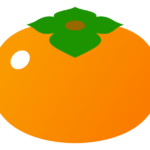新居に、僕のとは違った甘ったるい煙草の匂いが住み着くようになるまでには、そう時間がかからなかった。
ホテルマン時代のマンションから、さほど離れていない家賃4万円也のボロアポートへの引っ越しは、冴の手伝いもあって、呆気なく終わった。
その直後から彼女は僕の新居に入り浸るようになった。転居の際、持ってきたのは最低限の電化製品と寝具、一応こだわりのあるクローゼットを埋めることのない量の服(その殆どが千円以下で買った古着)、所有する全てのレコードと、コロムビアのGP-3(ポータブルレコードプレーヤー)、その他、中身も忘れてしまって開ける気力も起らない段ボール数箱、で全てであった。
「ねえ、私がもしずっとここに住むって言ったら迷惑?」
「あのう、それって求婚ですか?」
「いいえ。求婚では御座いません」
その頃二人の間では、突発的に堅苦しいやり取りをすることが流行りになっていた。あくまでも真顔で、真摯に、馬鹿真面目を装うのである。流行りなんてものはどれも傍から見るとダサい。客観視は事を白けさせるだけである。
「いいです。許可します。ですがね、冴さん、音楽をかけてくださいませんか。もしそれが求婚なのだとしたら、あまりにも質素なサウンドスケープではありませんか。ええ、実際、そうでしょうに」
「いいえ。求婚では御座いません」
冴は床に平積みにされたままのレコードの山からワンダ・ジャクソンを選び抜き、GP-3の上に乗せた。レコードに針を落とす動作がスムーズなのは、それが習慣だからなのでしょうなあ、と僕は彼女を誇らしく思った。このようにレコードを扱う同世代の女性を見たのは初めてだったのだ。
イントロは軽快なギター。意地の悪そうで、蠱惑的な声が歌い出した。
「それでは誓いのキスを」
「いいえ。しません。なぜなら求婚してはいないのですから。それより、求愛してもよろしい?」
「それはつまるところのロックンロールですか?」
「ダサいこと仰りますね。しかし私は諾々よ。さああなた、抱いて下さい」
「ダサいこと仰りますね」
僕は彼女にキスをした。彼女は言った。
「……愛なのですか?」
その言葉は何故か、彼女が彼女自身に問うているように、僕には聞こえた。
そしてその時感じた違和感は、間違っていなかったのかもしれない。
目覚めると冴の姿はなく、何が入っているのかも忘れてしまった段ボールに、太いマジックで〈実家に帰ります〉と書かれていた。
うちにマジックなんてあっただろうか? ―そんなんどうでもよいことです。
僕はそこで初めて彼女の実家がどこであるのかも知らない自分に気づき、ただ彼女がいないということ以上の不安を伴った虚無感が、開けっぱなしの窓から注がれる風と相まって、背中の寝汗を、不気味に冷たく感じさせた。
その文字には、〝真顔で、真摯に、馬鹿真面目を装う〟ときの遊び心を感じ取ることはできなかったのである。それはたしかに何かを訴えかけている、公衆便所の落書きのような力強い筆跡であった。
元はといえば彼女が家族のことを話すことを嫌うところがあった。とはいえ、仮に彼女が話したとしてもその対価となる話を僕は持ち合わせていないのだが……。僕が家庭の話を振ると、彼女は話題を変えること一心になり、その次に吹きかかるであろう自分に対する同じ話題を事前に防ごうとでもしているかのように感じることが何度かあった。だからこそ彼女が〈実家〉と言う文字を書き残していったのは不自然であり、そこには何か重大なことが隠されているような気がした。僕はベッドから転がり落ちるようにその段ボールに近寄って、変わるはずのない文字を何度も読み直した。焦点をずらすと、一本の棒になって安心した、のは束の間、何か行動を起こさなくてはという思いは、目先のガムテープに向き、箱の中身はなんでしょう? なんて自分に問いながら封を開けると、僕が感じた不自然は、正しかったということが知れた。
なかには、ただぽつんと、『あなたも心理学』が入っていた。
寝ぼけた頭を振ってみても、この本を段ボールに入れた覚えなどなく、むしろ昨日までは自分の鞄に入っていたはずであるという記憶が次第に確かなものになっていくだけだった。
つまり彼女は僕の鞄からそれを取り出し、段ボールに入れ、封をし、その上にメモを残したということになる。
そんな誰でもできるであろう駄推理の後に残ったのは、ただ一つ、なぜ? という問いだけであった。
私立探偵失格。
「愛なのですか?」
たしかに鼓膜が揺らされるような昨夜の彼女の言葉が、何度も頭の中で反響した。
僕はしばらく考えを巡らしたが、答えに手の届かないもどかしさだけが強まるだけであった。分かったことは、その答えは冴しか知らないということだけであった。彼女すら知らなかったらきっと楽なんだろう、と思った。
考えすぎかもよ。
彼女がそうした必要性すら僕には分からないのであった。
人の気を知らず、目覚ましが陽気に鳴り響き、今日が出勤日であることを思い出した僕は、どこか遠い国の無関係の儀式に紛れ込んでしまったようなシャワーを浴び、〈へそ〉に向かった。
通勤途中、何度か冴に電話を掛けてみたが、繋がることはなかった。
会得した。
成程僕は知らぬ間に、彼に成り切っていたのである。それは全て冴のお陰で。即ち冴は酒と同じ役割を果たし、僕を僕でいさせないことを僕に課した。それも何も抵抗や反発なしに、である。酒を飲むときの引け目のような感覚を、彼女に抱いたことはなかった。彼女は上質な酒。僕を狂わせる。ほう。狂う? そりゃどうゆう意味だい? 素面のときのほうが、よっぽど、クルッテイルではあるまいか。君はイマ、イヅコ? イズコ? どっちだっけ? 僕はまた遺書らしき文章を書き連ねなければならないのですか? どうしてあなたは消えてしまったのです?
ばれましたか、ええ、僕はシコタマ、酒を飲んだのです。そうするしか、他に手がなかったのですから。人には手が二つありますね。あなたも二つありますか、そうですか、で、それがなんですの? 三つあったら、僕以上の、普通の人間以上のことが、できるとでも仰りたいのですの? だいたい、あなた、ってだれなのです? それよりさ、普通ってなんですの? 一体、誰が基準やねん。出てこいよ、われ。日本語は不思議ですね。いとも簡単にIがYOUが役割を果たすのですもの。
自分。そりゃだれのことだい?
ああ、日付を書き忘れていましたね。日記には日付が必要なようなのです。書かないと怒られちゃうわね、って、誰に?
七月二十一日。
これで満足かい?
冴冴冴冴冴冴冴、これは恋? それとも愛?
愛なのですか?
はっはのはははっ、愛なのですか?
僕は見つけましたよ。見つけてしまいましたよ。ピンク色の蛍光ペンで、なぞられた文字を。その横に書き加えられた文字を!
「おれ(私の母)は父を殺したかった。だからあんな行動をしたのだし、後悔はしていない」
『あなたも心理学』の冒頭に、冴、あなたは、ルビを、そう(『私の母』と)書き足しましたね。
僕はググりましたよ。次第に、客観的に見ようとしても震える指で、『あなたも心理学』と検索しましたよ。でもね、全くヒットしないのですよ……そうして最後のページを開いた時に悟りましたよ。
この本は、ここにしかないのだということを。
だっておかしいじゃないですか、最後のページを開いても、そこにあるはずの著者や発行者の名前、印刷、製本、デザイン、©、値段―これらを総括する言葉を知らない自分に今、恥と苛立ちを感じております―なにも書いていないのですよ。
いや、なにも、と言うのは嘘ですね。
そこにはただ一つ、英語の詩が書かれていますよね。
Life hurts a lot more more than death.
笑っちゃった!
訳が分からないことって、斯様にもおもしろいのですね。
斯様にも!
ひひっひひひ、斯様なんて慣れない言葉を使って、僕はまたどこか別の僕へ飛んで行きたがっておりますよ。
「申し訳ございません。あいにく日本酒は切らしております」
はっはは、コンビニに行かねばなりませんね?
「下着での入店はお断りしております」
いっひひ、ズボンに脚を通さねばなりませんね?