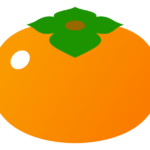『首』
空に穴が開いている。彼はそれを月だと言う。僕はそれを信じない。信じられない。
「あれは月なんかじゃない」
僕は三度目となる同じ言葉を彼に浴びせた。
「じゃあ何だっていうんだよ」
彼は溜息をついてから言った。
「あれは穴だ」
「空に穴が開いてるっていうのか?」
「そうだよ。そしてあの穴から漏れている光は、どこか別の世界の光なんだ。あちら側の世界には、僕らの世界とは違う世界があって、僕らとは違う生き物が住んでいる」
「宇宙人ってことか?」
「それはわからない。あそこは宇宙の外かもしれない」
彼はしばらく天を眺めながら黙っていた。
「でもどうして穴だと思うんだ?」と彼は思い出したかのように僕に訊ねた。
「だって、あれがもし月だとしたら、つまり物体だとしたら、落っこちてくるはずじゃないか」
背中にちくちくと何かが刺さり、僕は目を覚ました。仰向けに寝転んだ僕の目の前には雲ひとつない青空が広がっていた。僕は首を横に向け、周りを見渡した。そこはどこまでも続く広大な草原だった。そしてあることに気がついてはっとした。肩がないのである。僕は手で肩に触れた。肩があった。でも、僕の視界に肩はなかった。僕は何が何だかわからず慌てて立ちあがった。しかし、すぐにふらふらとしてしゃがみこんでしまった。そう、確かに僕は今、しゃがみこんだ。でも立っているような気がしてならなかった。それも竹馬か何かに乗って。目前に広がっているのは、高いところから見た風景だった。僕は恐る恐る下を向き、自分の身体を確認した。頭から遠く離れたところで僕の胴体がしゃがみこんでいた。そしてその胴体に向けて、一本の白い物体が伸びていた。僕は一瞬それが何なのか理解できなかったけれど、それは明らかに僕の首だった。
首が伸びている。
僕は首を触ってみた。二メートルほど下で腕は僕の意思通りに動き、指先が首の付け根に触れた。僕はその一部始終を見下ろしていた。もし指先が首に触れる感覚がなければ、きっと僕はそれが自分の身体だと信じることができなかっただろう。
首が伸びている、のである。
僕はもう一度立ちあがってみた。なんとか立ちあがることはできたが、歩いてみるとふらふらとしてバランスが取れず、転んでしまった。仕方なく、僕は四つん這いになった。これじゃあまるでキリンじゃないか、と思った。少し離れたところに大きな――といっても、今の僕が立ちあがれば同じ背丈ほどだが――木があった。その木には赤い実がついていた。僕の視力ではそれが何の実なのか判別できなかった。そして、その実を見ているうちに、ひどく腹が減っていることに気がついた。
やっとの思いで木の近くに辿り着いて見てみると、それはリンゴだった。僕は食べごろのリンゴを探し、それに手を伸ばしてもぎ取ろうとした。しかし到底腕がリンゴに届くことはなかった。少し考えれば分かることだが、なにせまだ頭と腕との距離感覚が以前のままだったので、眼前にあるリンゴは手を伸ばせば取れると思ってしまったのである。僕は今度は下を向きながら、もう一度リンゴに手を伸ばしてみた。二メートルほど下で、ぴんと腕が伸びた。阿呆のようであった。
僕は仕方なく、口を大きく開け、そのままリンゴに齧りついた。しゃきっという音が響いた。僕はそれを大切に味わってから飲み込んだ。長い首の中をリンゴの欠片が滑っていく感覚がしっかりとあった。それは快感だった。僕はもう一口齧りつき、またその感覚を楽しんだ。すぐに実はなくなって、蔕だけがぶら下がった。それでもまだ空腹は満たされなかった。
一体幾つ食べたのだろうか、夢中になっているうちに、僕は全てのリンゴを食べてしまった。満腹になると、僕はその場で寝ころびまどろんだ。
「ニュートン、朝よ、起きなさい」
母親の声で僕は目を覚ました。そこは自分の家の自分の部屋の自分のベッドの上だった。
「早くしないと遅刻するわよ」と母親は怒鳴った。
僕は時計に目をやり、寝坊していることに気付くと、飛び起きた。その瞬間に脳天に激痛が走った。天井に激突してしまったのである。いたた、と僕は頭を抱えた、はずだった、が、僕の、手は、二メートル下で、中空を掻いただけであった。
「何してるの、あんた何年この家に住んでるのよ」
振り向くと、そこには首の長い母親が呆れたような顔をして四つん這いになっていた。
「起きて早々に二本足で立とうとする馬鹿がどこにいるのよ」と母親は言った。
僕は言葉を失った。ふとベッドに目をやると、それは僕の記憶しているものの倍以上の長さがあった。
まさか、と思って、僕は四つん這いで走り、家を飛び出した。
外には草原が広がり、ぽつぽつと何軒か家が建っていた。そして何本ものリンゴの木が生えていて、そこに何人もの人が群がっていた。彼らは皆、首が長かった。
「遅刻しそうでも朝ご飯は食べなきゃだめよ。今日はあの木のリンゴだよ」
玄関から出てきた母親が僕に言った。
母親が指差したリンゴの木の真上に、白い月がうっすらと浮かんでいた。僕はそれを見て、いつだか見た夢を思い出した。その夢の中で、僕は何故か月のことを穴と言い張っていた。そしてその理由を、落っこちてこないからだ、と言っていた。
そういえば、どうして月は落っこちてこないのだろうか、と僕は考えた。
地上では首の長い人たちがリンゴに齧りついていた。
そんな光景をぼんやりと眺めていると、僕は閃いた。
そうか、きっと月にもリンゴのように蔕がついていてぶら下がっているんだ。
「ニュートン、急ぎなさい」と、また母親が怒鳴った。