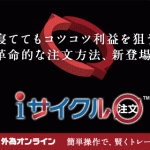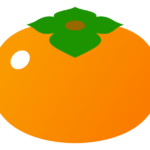夏目漱石『吾輩は猫である』
だれもが一度は読んだことのある言わずと知れた名作。
夏目漱石は、39歳でこの作品を書き、40歳でこの世を去った。
この作品に込められた思いとは?
一見ふざけっぱなしのこの作品。
漱石は最後の最後でこう綴っている。
「呑気と見える人々も、心の底を叩いて見ると、
どこか悲しい音がする。」
ユーモアが繰り返されたあとに、
都甲幸治と町田康が『吾輩は猫である』を語った
アメリカ文学研究者であり翻訳家の都甲幸治と、
いまや日本文学の第一人者でありる町田康が、
『吾輩は猫である』について対談した。
今回は、そのとき二人が語っていたことを思い出して書いてみる。
都甲は上記した漱石の名文についてこう考察する。
「500ページぼけてきて、最後に悲しみを表現している」
それに対して町田は、漱石の思いを段階的に予想し、違った考えを示す。
①「最初から絶望」
⇒②「おちゃらけてみよう」
⇒③「ますます悲しくなってきた」
この作品を書いて1年でなくなった漱石。
怒涛のユーモアの最後に、
うつ病であったとも言われる彼の心の闇を垣間見ることができる。
猫を主人公にするということ
動物が主人公として登場する作品を多く出版している町田康。
主人公を動物にすることで、文章のあり方が変わってくるという。
町田康は、執筆時のエピソードで、
猫を主人公として描いた時の小説の面白さを語った。
「猫なで声」という言葉を書こうと思ったとき、
彼は、「ちがう」と思い、
「猫なでられ声」だと訂正した、という。
そこに読者としては、ユーモアを感じるようになる。
あるいは、
「新幹線に乗って大阪に行った」
という文章を書こうと思ったときに、
「新幹線というものがあるらしいが、」と前置きを置かなければならない
とその「制限」を語る。
制限があるからこそ、窮屈になり、それを打ち破ろうとするエネルギーが笑いを生むのではないか。
漱石においても、『吾輩は猫である』の冒頭で、
窮屈をユーモアに変えている部分がある。
吾輩はここで始めて人間というものを見た。然もあとで聞くとそれは書生という人間のなかで一番獰悪な種族であったそうだ。
猫目線で語ることで、自分自身(書生)を皮肉している。
町田康が語る「文学の意味」
町田は、自分で作品を書くときに、
自ら笑いながら書いているという。
そうして自分の正気を保っているのだという。
漱石もそうした意味合いを持ちながら『吾輩は猫である』を書いたのではないだろうか。