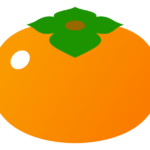「これをうちで買った? ―ああたしかにこりゃうちで売っていたもんだ」
背表紙に貼られた値札シールを確認すると、〈有賀書店〉の店主はそう言って頷いた。
「この本を買いとったときのこと覚えてませんか?」
「買い取ったとき? なんでそんなことを」
「もともとの持ち主を知りたいんです」
「いやあ、そんなこと言われてもですね、毎日のように何冊も買い取っているんでありましてな、お客さんの顔なんていちいち覚えちゃいませんよ。何の本が置いてあるのかすら覚えてないのですから」
店主は面倒臭いことを露わに答えた。
「はあ」
「そのう、何か問題でも御座いましたか?」
「ああ、いえ別に。ただ、この本、ないんですよ他に。いくら探しても見当たらないんです。情報が」
「はあ。古い本みたいですしなあ」
「そうゆうことではなくてですね……、出版されていないのでは? と思いまして」
「ほう、ちょっと貸してもらえますか」
店主は丸い眼鏡を外し、『あなたも心理学』のページをぺらぺらと捲りだした。机に置かれた眼鏡の鼻あてが、必要最小限の脂で光っている。情報を求めて、わざわざ店まで来た挙句、そんなことに意識が移ってしまっていることに気がついて、何のために、と、自分が馬鹿馬鹿しく思えてきた。
「なるほど、たしかにおかしいですな……出版元の記載がない」
「買い取りはどのように行っているのです?」
「いやあ、申し訳御座いません。本来確認しなきゃならないのですが、あまりに量が多かったりすると私も手を抜いてしまうことがありまして……長年古本屋をしてると分かるんですわ、違う違う、これは言い訳ですね……売れる本と、そうでない本。たぶん買い取った時に売れない本だと思ったんでしょうな、そうゆう本は、十円で買い取って、百円コーナーに置いておくんです。いや、ほんとにただの言い訳みたいになってしまいましたね……すみません」
流石に気まずくなったのか堰を切ったように言葉を紡いだ。
「別にあなたを責めているわけじゃないですよ。で、何も、分からないんですよね?」
「すみません、思い出せません。もしあれでしたら返金いたします」
その提案を断った僕に本を返すと、店主は申し訳なさそうに眉を下げた。
「もしあれでしたら、何か分かり次第後日連絡いたしますが」
「紙とペンありますか?」
僕は店主が差しだしたメモパッドに電話番号を書いて渡した。
「なにか思い出したことありましたら、ここに電話してください」
何も言わずに店主は受け取り、慣れた手つきできれいに一枚のメモを引き破り、難解な数式に対峙した数学者のような顔つきで、十一ケタの番号を見つめてから、静かに頷いた。
外に出ると、平穏な顔たちの間を縫うように歩きながら、僕は本を開いた。僕にはできない、殆ど無意識に何かを演じている顔たちを見るのは億劫だったのである。
小説を、こんな風に読むことは初めてだった。
まるで美容室で、話しかけられたくない一心で、仕方なしに読む雑誌のように、ランダムに開かれては、捲られ、進んでは、戻って進む。見開きのページから自分に有意義な事柄をさがす視線は、密林の中から行方不明者を捜す警杖の動き。そんな小説家にとっては冒涜とも言うべき読書を、僕は延々と繰り返す。ふと思い出すのは、センター試験、「国語」。学生がテストに向かう態度を、小説家は望まない、と、気づく。そうか、そうだ。
んじゃ有意義な事柄って?
脳内で、根本的な問いが突沸する。飛び散る疑問を僕はむしろ避けながら進む。
僕のなかに答えはない。
本のなかには、あるかもしれない―それすら断定できない。
答え。例えばそれは、小説家が、冴の母親であることの証明、或いは、冴の居場所の手掛かりのことである。
僕はそれを知って何がしたいのであろう? 冴はいなくなった。それで物語は完結した。お・わ・り。ジ・エンド。Fin。まるでダサいけど、それでいいではないか。所詮、ある一つの恋が終わったにすぎない。今となっては、もはや関係ないことだ―いや……違う、のか?
結局何も情報を得られずに、その日は泥酔の末、気絶と変わらぬ眠りに落ちた。
本当は「その日は」ではなく、「その日も」であることは置いといて下さいよ、頼んます。
無意識に机をたたく指の動き。このリズムの根源ははたして。
ひっきりなしなエンジン音、間にクラクション、鳩の鳴き声、人の足音、ということはということの鳩の足音、大街頭スクリーンの広告、金の臭いがする音楽、流浪する住処・ティッシュのチラシ、ラーメン屋の黄色い活気、瓶の流転、若づくりが擦るライター、火ぃつかなぁい、鴉声、舌打ち、罵声、舌舐め、嬌声、脱いだハイヒール、脱がされたハイヒール、ポン引きのハスキーボイス、不分明で微かなジャズ、生唾ごっくん、エトセトラ。
「いくらだ」「万単位」
FromポケットToポケット
エントロピー増大と万物流転。
乱れた秩序のなかで聴くリズム。
心拍が埒外なオフビートを刻みだす。
テイヤは自分に言い聞かせるように呟いた。
「お守りだ。お守りだ」