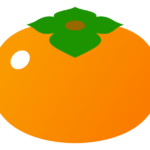イヤホンを着けてiPodくるくる、指はストーンズを選んで止まる。
コンガがサンバ調のリズムを刻み出す。
コーヒーを持ち上げ飲むと、本の入ったビニール袋の上に、水滴が取り残される。僕はそれで指先を洗う。ジーパンで拭く。
何も書かれていないビニール袋から本を取り出してみる。『あなたも心理学』。あなた〝も〟って何やねん。というかこの場合、心理学って名詞ってよりは動詞ですか、命令形?
「ねえねえ筆者、動詞ですか?」
再び、となじい(隣の爺さんのことである。名詞である)の視線。お詫びの首振り。
頭を下げてばっかりである。
それでは社会から逃れた意味がない。となると、これは、人間性の問題か、性格か? ほな、性格とやらを分析して、正せばええではないか。ってかさっきから気になってたんですけど、その関西弁風弁なに? いや大卒でやっと手にした職で初めて配属されたのが大阪だったもので。ふうん、で、性格は何から作られるの? そもそも先天? 後天? 後者じゃねって、だとしたら家庭環境? 僕をつくったのは誰?
で、テーブルの上には心理学の本。〈心理〉という文字がぴかーんと光って見えたのです。なんとま! 日本語では何というのだろう、セレンディピティってやつは。
ぺらぺらとめくりながら二本目の煙草を吸って、いつのまにやら灰だらけの机上。悪いのは僕ではなく、ほら見てよ、灰皿が小さすぎるのである。店員さん、きっとあなたが後で拭いて下さるんでしょう。ごめんなさい。
嗚呼、また謝罪!
そうして知れたのは、この本がどうやら学習もんでもハウツーもんでも自己啓発もんでもなく、小説であるということ。
そもそも小説の定義すら知らないけれど。
〈カフェレストラン・へそ〉での皿洗いの職を手にしたのは、その翌週、日曜日のことだった。日曜日に働けるのはいいね。逆に平日に休みが来るんだから。人ごみのない休日が待っているのだから。
僕がもともとホテルで働いていたということを知ると、店長の萬羽さんは、
「いまちょうどホールスタッフも足りてないんだけど、よかったらそっちにしない? ホテル業の経験あるなら接客得意だろうし、こういうこと言うのもなんだけど、皿洗いなら障害者雇用のほうが安く雇えるんだよね。それ会社の方針でもあるし。ちょうどこないだ電話あって、来週面接するんだけどさ」
と言った。萬羽さんは僕の一つ上という年の近さからか、初めから気さくに話してくれた。そしてその反面、本心を隠すということをしなかった。
「僕はどちらでも。家賃が払えればいいんで」
安心感からか、嘲弄からか、僕もまた調子に乗って本心を話した。同年代のしっかり者を前にして、自由気ままな生活を送る自分に羞恥心をしっかり感じていますといった体で、少し伏せ目がちにすることを忘れずに。
萬羽さんはそんな脆弱な演技を真に受けたのか、立ち上って僕の肩を軽く叩いて言った。
「じゃあ希望とは違うかもだけど、ホールとしてよろしくね。ほかのスタッフに接客のコツを教えてやってちょうだいな」
彼は不自然な白い歯を覗かせて無邪気ともいうべき笑顔を浮かべた。
「初日決まったら電話するね」
その笑顔のなかには、一人のどうしようもない男をおれが救ってやったんだという満足感と、ほんの一振りばかりの期待感が込められているように見えた。彼もまた自己充足的な人間。例の大学の奴らと変わらない。
僕は思った。こいつ莫迦だな。
六月九日
『あなたも心理学』を読む。まだ三分の一も読んでいないけれど、アタリかもしれない。というのは、これまでも本を読む中で自分がその物語の主人公、あるいは筆者に自分を投影、移入し、その偽物の自分を楽しんできたし、それこそが読書の楽しみだったのだけれど、この本は主人公やら筆者とは別に、彼らを親とするような人格が自分のなかに出現し、本を手放した後も、その新しい人格は己を矢にして、常に僕に向けて弓を引いたまま、機会を逃すまいと、自分のなかでずっと揺曳しつづけているように思うのである。
というか、思ったら思えたのである。
そうして、いつか弓が放たれる。僕は理由もなく確信する。
「おい、あんた、エアバッグみたいよ。見えないところで狸寝入りしながら、常に準備万端なんだろ」
と。
暇を埋めるために本に陶酔してみた挙句の過言ですかもね。
それにしてもこの本がもつその魅力はどこから溢れてくるのだろう、なんて思ったら、またほら、思えるんだ、それにしても。
しかし問題が一つあります、と僕は人差し指を立ててみる。
それは酒を飲まなきゃならないということであります。酔わなければ弓が放たれても意味がない。ある程度、本来の理性を溶かしてからではないと、新しい人格は、僕本来の人格に跳ね返されるのであります。
こうしていま僕は日本酒を飲んでいるわけは、そこにある。
初めての感覚だった。珍重すべき感動だった。そして僕はその新しい人格―僕はそいつを彼と呼ぶことにした―に頑張ってもらおうと思った。そう考えると全てがどうでもよくなった。どうでもよくなるということは、僕にとっての最大の価値である。
それはまるで、募金だけして実際の活動はあんたら、なんちゃら団に任せますといったようなある意味無責任の態度。気楽ながらも歓迎される態度。楽と楽しさを混同した態度。
注ぐ。
そうして僕が彼になるときには、彼が僕になった。常に僕は僕の上。それは時間に似ている。明日というものが言語上では存在するけれど、実際には今日の上にしか立てない。あの感じ。明日だったはずのものが、今日になる。明日に触れられるときは一生来ない。無限に今日。永遠に今日。まさしくその感覚と同じだ。
僕は物語を回想する。『あなたも心理学』は主人公の女子大生・民恵のモノローグから幕を開ける。