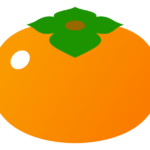太宰治は常におどけている。
彼の『小説の面白さ』という文章を
読めば、彼が何故おどけ続けたのか、
わかるような気がする。
「小説と云うものは、本来、女子供の読むもので、いわゆる利口な大人が目の色を変えて読み、しかもその読後感を卓を叩いて論じ合うと云うような性質のものではない」
と冒頭で、太宰は断言する。
小説というものを難しく捉えられてしまえば、
太宰の「おどける」場所が失われてしまう。
まるでそれを恐れているかのようだ。
さらに、こうとまで言う。
「襟を正しただの、頭を下げただのと云っている人は、それが冗談ならばまた面白い話柄でもありましょうが、事実そのような振舞いを致したならば、それは狂人の仕草と申さなければなりますまい。」
こうして太宰は、小説の、
あるいは太宰自身のハードルを下げていく。
この辺がなんとも上手いのが太宰治である。
その態度は一貫し、例え話に続く。
仕事に行く支度をしながら、亭主が女房に、
「この頃どんな小説が面白いんだい?」
と興味もないのに聞く。
亭主は女房の「ヘミングウェイ」という答えを聞き、
適当に「ふむ」と言い、仕事に出かける。
その夜、亭主はサロンで、
女房から聞いたばかりの小説について、
知ったかぶりをしながら語るのだ。
太宰曰く、
「小説と云うものは、そのように情無いもので、実は、婦女子をだませばそれで大成功。」
余談として、最後にこんな話がある。
太宰が島崎藤村の『夜明け前』を読んで、
眠くなって寝た。
その日、太宰はその小説とは何ら関係のない夢を見た、のだという。
因みに、島崎藤村は『夜明け前』完成のために、10年かけた。
その事実を後になって知った太宰は、
「ふうん」としか、思わなかったとしている。
この文章は、
「その作品の完成のために十年間かかったと云うことでした。」
と、あっさり終わる。
小説を「面白くない」と言うことが、
太宰の手にかかれば、
小説の面白さを一番に教えてくれる言葉にかわる。
太宰の魅力ここにあり。