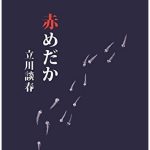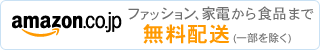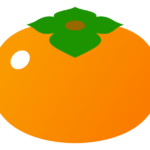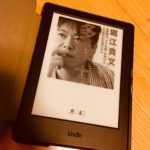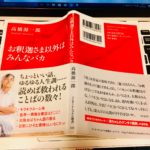休みの日には、紺色の作務衣を着て、下駄を履いて夜道を散歩する。毎晩こいつを着ているために洗わず仕舞いとなり、覚えのない汗の匂いが染みついている。自分の匂いだからであろうか、不快感は全くなく、むしろ僕を落ち着かせる。夏がすぐそこで待っているこの季節には、胸元に侵入してくる風が、日中に火照った身体を癒してくれる。
家から五分もしない距離に、小学校がある。人気のない学校はいつでも奇妙で不気味だ。陽のある時分には幼い人々の生活の中心であるはずのそこには、夜になるとなんの価値もない。校庭に吹く風もできたら避けたい場所であろう。或いは本当に避けてきて、その風を僕が受けているのかもしれない。まるで巻き添えの被害者みたい。そんな愚考さえしたくなるのは酔っているからであろうか、あろうね。僕は学校の前にある公園で二本目のビールと、二本目の煙草を吸う。いつから数えて二本目なのだ? どうしてそうして断定できるのだ? 僕は知らず間に人生を区分している自分に殆ど腹が立つのと同質の、しかし複合的な感情を抱く。校庭よりも広い公園のどこか遠くで、スケートボードで遊ぶ人の音が聞こえてくる。地面をウィールが滑走する音は暴力的で痛々しい。時折するあの打音らしきは、着地音か? 蓋しその通りであろう。なんて直截的なメッセージであることか。
大学時代に僕はゼミでサウンドスケープ(soundscape)について学んだ。サウンドスケープは、ランドスケープ(landscape)から変化した言葉で、「音風景」を意味する。
例えばフィールドワークでは街中で耳を澄まし、そこにある音の世界を、風景を、感じるのだ。平日の昼間など、だれも意識していないであろう音たちに集中すると、次元の違ったところから街を眺めているような錯覚を覚える。一回の青信号で三千人が渡るとされるスクランブル交差点をそうして俯瞰すると、人が無理して人らしいとされる人を演じていることに気づかされる。それは殆ど滑稽である。僕は自分もそのなかの一人であることを忘却して、聴こえてくる音を紺色のノートに箇条書きする。ハイヒール、キャリーケース、クラクション、街頭演説、広告、飾りばかりの草木、シンガーソングライター。せわしなく発せられる音たちのなかで、人々は何故か皆、生き急いでいるふうだ。まるでその日ばかりと宣告され、どうしようもなく、ただ命を惜んでいる人たちの忙しない呼吸に聴こえ、見える。聴覚は視覚に影響を与える、らしい。
僕は生き急いでいる人が嫌いである。余裕のない人が嫌いなのだ。人間がつくったシステムに人間自身が吸い込まれていくようで。そんなことを考えたのちに、いいや、人間その全てが嫌いなのではないかという思いによく至った。いま考えると、何よりもその思いを確認するために、いつも街の音に耳を澄ましていたのかもしれない。
夜は違う。ちゃう。寝静まったなかで立つ数すくなな生活音には余裕がある。朝になればみんな忘れてしまうのだろう心地よさが、そこにはある。夜がどこか、うらさびしいのは、朝が来てしまうからなのかもしれない。夜の宿命。昔は心を〝うら〟と読んだ、という話をいつだかラジオで誰かが話していたことを、ふと思い出した。
初めは漠と、次第にカメラのピントを絞っては、冴を想う。ぴたっと合った時、楽器になった僕の心が身震いして気弱な音を出す。僕が彼女に惹かれているのは、そういった意味で、彼女が常に〝夜〟を保っているからであろう。彼女はいつでも〝夜〟であり、いつでも〝朝〟を嘲弄しているかのように見える。そしてそんな彼女に惹かれている事実が、僕が〝夜〟を保てない人間だということを明証する。
いいかオレ、オレはオレが嫌いだ。そうか? そうだ。
天気予報によると「例年に比べて遅い」らしい梅雨の嚆矢か、不意に雨が降り出した。初めに雨は埃を舞い上げ、すぐに抑え込む。まるで徒労に思えるその自然の一連の動作が一気に行われると、僕は砂ぼこりの残り香を強制的に感じ取らされる。雨宿りをしようとあたりを見渡しても適した場所がなく、僕は背丈ばかりのフェンスをよじ登って、小学校のなか、幅の広い滑り台の下に駆け込んだ。そのときふと、滑り台の鉄板の上に、滲んだ月が浮かんでいるのが見えた。空を見上げると、厚い雲の隙間から、一つ目のような月が覗いている。まるで不法侵入者を捉え、動揺の裏で歓喜するスポットライトの様に。
手についた雨を作務衣の脇で拭き、鞄から紺色のノートを取り出して日付を書きこんだときに、今日が七夕であることに気がついた。慣例に従い、願い事を考えだしている自分が、このノートを書き始めたときの自分とは別人になっていることを、見て見ぬふりをするようにしながら、それでもたしかに、認めだしていた。
七月七日
滑り台に映った夜空を、僕は滑ってみるんです。
月の黄色いペンキが、お尻についたら、おもしろいのにな。
第1章―「ピグマリオン効果」
さて諸君、というのは読者諸君。あなたたちの戸惑いを私は確と感じていますよ。いいえ、読者諸君とやらが将来できるならの話ですがね。
さて諸君、というのは読者諸君。私が、このように鍵かっこで題を掲げ、話を書き綴ろうとしているわけは、おわかりですか? ほう、「わかりっこない、そうして文字数を稼ぐのはやめろ」とは、なかなかごもっともなご意見ですこと。
さて諸君、というのは読者諸君。私は倉知さんの傀儡ですか? なぜ、ってこうして彼に言われた通りに私はいま、原稿を書いているからじゃない。
「投書の文章を、用語ごとに何章かに分けられないかな?」
と言ったのは、そう、倉知さん。
「へへい」
これ、私の返事。いかに私が彼をあしらい、見縊っているかがお分かりいただけましたでしょう?
かように従順な私がいつまで続くことやら。
「戯言は早々に、本題に入れ」と彼は言うでしょうね。でもあなた、思い出して……
この戯言に魅かれたんでしょうに。違う? 素直じゃないわねえ。意地悪はこの辺で。入ります。
あれは高校時代のことと記憶しております(どう? それっぽいでしょう?)。
というのは嘘で……と書いたら怒りますか倉知さん。でもね私は、こんな文章でもあなたは認めてくださるんでしょうって、信じているわ。だってあなたは私を好きになって下さったのだもの。
「どうなってもいい。君が書くのなら、それが僕の望むものとなっているだろう」
いいえ、こんな堅苦しい言葉ではなかったけれど、あなたは確かにそのようなことをおっしゃったわ。私はいつでも聞いた言葉を、自分の言葉に置き換えて記憶する癖があるの。ああ、倉知さん。私の倉知さん。あなたはいつでも私を認め、救ってくださるんでしょうね。
私はここまでの原稿をもって、いつものロック喫茶に向かった。
その店は、一昔前まで映画館やジャズ喫茶とともに文化の中心地として栄えていたという現在はラブホ街と化した薄暗い路地に静かに佇んでいる。懐古にはどうしても寂寥感が付き纏うことを、皮肉とともに表している。
蔓だらけの見た目からして重たいドアを開けると、六十年代のマジービートがこぼれだし、ボブ・ディランのおおきなポスターが顔を出す。ここにだけは、栄えていた時代の空気がまだ逃れずに漂っているのでは、と錯覚させる。
倉知さんはいつでも、二階の一番奥の席に座っている。私はそれを知っていて、知っていることに喜びを感じるとこを知っている。「スピーカーに一番近いから」というのがその理由らしい。彼はいつも黒い丸っこい眼鏡を掛けて、居眠りをしているかのように俯きながら、本を読んでいる。初めて会ったときもそうで、それでも私が、これまでにも疑わしい男を信用するに至ったのは、リバプールサウンドがお互いの趣味で会ったことが功を奏したとしかいいようがない。なにせ、その日は、本題であるはずの「本をつくろう」なんて話は殆どせずに、九十%以上は、音楽の話をして、あの私が一日にして打ち溶け合ってしまったのだから。そして不思議なことに、その九十%の内の八十%ぐらいは、既に忘れてしまった。ただ仲良くなれたという事実ばかりが残ったのである。
私は俯きの彼に気づかれないように足音を殺しながら近づいて、届くか届かないかのぎりぎりのところから、スピーカーに住み着いたドラマーがちょうどシンバルにスティックを振りかざすタイミングを見計らって、封筒に入った原稿を彼の足もとめがけて投げつけた。
その時の彼の驚き様といったら、まあ無様、まるで本当に居眠りをしていた男子生徒が教室でぴくんとなって机の上の鉛筆を落としてしまった様子を連想させた。その恥ずかしさと恐怖感が相まった少年の顔、にふしだらな生活を体現化する役を任せられた無精ひげが生えている。そうしてなんとか落ち着き払った態を取り繕いながら、
「やっぱり。民恵か」
と言った。
彼は初めから私を民恵と呼んだ。そうすることでお互いの距離が縮まるのだとでも思っているかのように、頑なに。私にはなんだかそんな姿が可愛らしく見えた。自分の仕事のために少女と出会って、自分の名誉のために少女を名前で呼んでいる。まるで人間らしい業をそこに見た気がして、愛らしかった。でも、欲は双方向だったのだと今になっては分かる。きっと私も生き甲斐を見失った時にふと現れた彼に、無理にでも好感をもってやろうと思っていたのだと思う。それはまさしく義務みたいに。
会合から二曲が流れ終わるころ、彼は読み終わった原稿を封筒に入れ直し、三白眼を演じるための上眼づかいで私を見て、にやりと笑った。
それは私の文章を彼が認めた証拠であり、取りも直さず「ピグマリオン効果」が実証された瞬間であった。