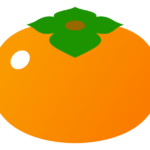作戦A。雷雨決行。天気・晴れ。
往々にして作戦Aが作戦Bより先行されるなかで、なぜ今頃になって作戦Aが決行されるのか? 単にそれは僕に勇気がなかったからである。怒られるのが嫌だったから、である。その前にああ、作戦Bのことを説明しなあかんね。古本屋に行くことだよそれは。で、Aがこれ。
〈へそ〉に入店する。である。
繁忙期を過ぎた午後4時半。その上、水曜日。はっは、店長は仕入れに出掛けるのだ。
「久しぶりです」
僕は平然を装って事務所に入った。
「あれれ、なにしてんの」
アルバイトの先輩が驚愕と困惑と侮蔑をないまぜにした口調で言い放つ。
「ちょっと忘れ物で」
「お前、どうしたの、最近来なかったけど。ってか辞めたのかと思ってたよ。ってか辞めたことになってるよ、お前ら」
「お前ら?」
「お前と冴ちゃん。付き合ってんだろ?」
「……はあ。店長怒ってました?」
「そりゃね。一気に二人いなくなるんだもん。そりゃ怒るでしょ、ってかむしろ笑ってたかな。『怒りの向こう側』とかなんとか言って」
本音を暴露しよう。店のなかでは口を揃えてというのでもなく冴との仲を秘密にしていた僕は、二人の仲が知られていたことに動揺して、平然を装うことに余裕がなくなっていたのであーる。
僕は棚から抜き取ったファイルを落としてしまった。その瞬間、隠していたはずの動揺が表面化されたような気がして、また一層、鼓動が早まった。
「ってか忘れ物ってなんだよ?」
答える言葉も見つからないまま、僕は拾い上げたファイルから自分と冴の履歴書を抜き取って、冴のものを覆い隠すため、自分のを上にして、言った。
「これっす。返してもらっていいですよね?」
「はぇ? そんなもん返すもんじゃないだろ? ってか今さら要るわけ? そんなん」
「今度また面接なんで」
「使い回し? お前どこまでも最低だな」
のべつ疑問符の先輩は呆れたように笑った。
「店長には秘密でお願いしゃす」
「まったく『怒りの向こう側』って意味が俺にもわかってしまったよ」
僕は足早に事務所を後にした。「待てよ」という先輩の声を背に、僕は返した。
「お疲れさまです」
嗚呼なんと便利な言葉。
履歴書が示す住所は、家から電車で二十分あまりの距離であったが、全く馴染みのない場所であった。
その駅には降りた覚えがなく、当然周辺の風景を、想像を超えてあたまのなかに浮かび上がらせることはできない。それが冴と自分が分かち合えなかったことを示しているかのように感じられ、そこへ向かうことを躊躇ってしまった。
証明写真の冴の顔はほのかに笑っている。感情を抑えながら暫く見ていると、会ったことのない見知らぬ顔のような気がしてくる。
ふと憧れのアーティストに初めて会った日の夜のこと、あれは夢だったのではないかというほどの高揚の反面、会ってしまったことを後悔した少年時代を思い出した。なぜかは分からない。けれど、近くにいたはずの人が遠くにいってしまうのと同じ程度に、遠いはずの人が近くにいることは、残酷で遣る瀬無いものであった。
駅に向かう道すがら、とはいえ自分の家に帰ることも虚しく感じられたので、とりあえず喫茶店に入った。外観からは予想しがたいほど広い店内は、気が引けるほど〝お洒落〟な空間であった。僕はすぐさま、大学時代の知り合いの顔顔顔を思い出さなければならなかった。アイスコーヒーを頼み、ガラス扉で隔離された喫煙席に座った。あたりを見渡すと、そこには隅に「ほんのひと時、煙草を楽しみたい方へ」という張り紙の前にスモーキングスタンドが置いてあるのみで、灰皿が見当たらなかった。鞄から財布だけ取り出し、レジまで戻ると、店員は何も言わずに、灰皿を僕に手渡した。自分が欲していたものを知られていることは、なんとまあ恥ずかしいことよ。そんなことに恥を感じてしまうから僕は心の内を露にすることが苦手なのだろうね。灰皿には、恐らく出がらしであろうコーヒーの粉が敷いてあった。僕はまた例の顔顔―その途中で〈へそ〉から電話がかかってきたが、無論無視した―顔を思い浮かべなければならなかった。そのなかの一人の名前も知らないのに、である。いずれにせよ、僕の人生に、彼らはこのような形でしか登場しえない。彼らの方からすれば、登場することすら拒むのだろうけれど。
たしかな居心地の悪さのなかに、静かに好奇心が顔を出しかけて、頭を振った。
マグカップに五分の四のコーヒーと、フィルターが燃えかけるほど短くなった煙草、十二行ばかりの活字。また頭を振って、僕は店を後にした。急いでいるんだか否か、競歩のような態度は取りも直さず、傍から見りゃ不気味に属する動作、所作。同年代の一般人―って何?―が気を落ち着かせる場所に行くと、僕はいつでもこうして空間の諧調を崩してしまう。〝一般人〟からすりゃそりゃ目障りであろうけれど、僕は慣れないオプティミズムを絞り出して、「オフビート。オフビート」と呟いた。いいんだ、いいんだ。音楽の世界では邪魔のはずのものが逆に彩りを添えることだってあるじゃないか。
「おふびいと。おふびいと」
今度は、マリア様が現れて仰るのです、ってな感じで優しく言った。冬の宿酔の朝のコーンポタージュぐらいはほっとした。
店をでてコンビニで日本酒を買い、ストローを噛みながら、僕はやっと冴の元へ行く決心をした。
着いた。冴はいなかった。家はなかった。そこはただの公園だった。
僕はブランコに座って星を眺めた。いいえ、星すらなかった。
テイヤは空を眺めた。空はいつでもあった。ブランコが揺れた。前に進んで、後ろに戻った。前に戻って後ろに進んだ。隣の空のブランコは静かで冷たい。眠っているのだろうか。はは、死んでいるのだろうか。手を伸ばし、おい、と揺らした。カタカタしてすぐに止まった。はは、死んだ。嫌だねえ。死にたくないねえ。結局どこにも進まなくても、こうして揺れているだけで生きているように見えるんだねえ。簡単だねえ。
電話が鳴った。テイヤは消えた。
僕はブランコから飛び立ってポケットから電話を取り出した。知らない番号からだった。
冴冴冴。一呼吸置いてから、通話ボタンを押した。「ああもしもし」聞き覚えのない、男の声だった。
「いま時間大丈夫ですか? 〈有賀書店〉の者ですが」
「ああ。こんばんは。え? 何か分かったんですか?」
鼓動が高まった。
「いや、あの本、まだ持ってますよね?」
「ええ」
「そねがね。今日、あの本と同じ本を売りに来た人がいたんです。あれ、普通に売られてる本だったんじゃないですか?」
「え?」
「いや、あなたも持っているなら」
「ちなみにどんな方が、その本を?」
「若い女性でした」
「ほんとですか?」
期待が一気に高まった。違いない。
「染めているんだと思いますが、金髪のよく似合った細身の女性でしたよ。すらりとした。ええと、セキユキエさんという」
「名前を聞いたんですか?」
希望は一瞬にして崩され、薄れた興味から、僕は無愛想のような声になってしまった。
「ええ。いつもは聞かないんですけどね。お金のやり取りがあるという口実で、名前と連絡先を聞いておきました。それにお綺麗な方でしたので、へへ」
「僕のために?」
「まあ、そうですかね。どうせ先も少ない人生ですから。最後ぐらいは人のためになることも悪くありませんしね、ええ」
「急に何をおっしゃりますか。ありがとうございます。ほんとうに」
「紙とペンの用意はよろしいですか?」
僕は何がなんだか分からないままいつものすっかり草臥れた紺色のノートを開き、はいと答えた。
「大関のセキに、志と書いてユキ、そんで絵画のエです。セキユキエ」
そのあと、僕は電話番号もメモに取り、礼を言って電話を切った。
酔いの覚めた頭で振り返ると、ブランコはすっかり死んでいた。
『あなたも心理学』のなかで、民恵が父の死を回想するシーンが頭によぎった。
「眠っているのと死んでいるのを見分けるのは、呼吸があるか、心臓が拍動しているか。ただそれだけなんだね。その他は何も変わらない。身体の成分も境を越えたからといって別物になるわけじゃない。死という名の変態もしない。ただそれが動かなくなった時、私たちはなぜか〝普通は〟悲しむ。それだけ。よく考えれば不条理にさえ思えるし、まるで滑稽ですらあるよ。うん、笑っちゃう」
僕は二つのブランコを思い切り、一回転させる勢いで揺らしてから、錆ついたチェーンの叫び声を背にして、公園を後にした。