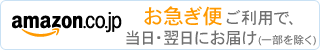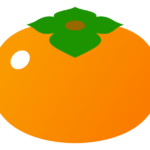『生きる哲学』 著:若松英輔
この本は、いつでも自分の足で確かに立ち、
新たな思索を切り開いた14人の「生きる哲学」を知ることができる。
「哲学」と聞くと、小難しく、机上で考えるイメージを持つかもしれない。
しかし、ここに書かれた哲学は、
誰もが既にもっているものである。
本の言葉を借りれば、
「人生の岐路に立った時、真剣に考え、誰に言うでもなくひとり内心で、これが私の哲学だと呟く」
そうしたものであるという。
つまり、哲学とは難しい勉学の後に獲得するものではなく、
既に私たちひとりひとりのなかに存在しているものなのである。
つまり、哲学はわたしたちとともに生きている。
だからこそ「生きる哲学」なのだ。
その自分の哲学を、伝えられる人と、そうでない人がいる。
この本で紹介される14人の方々は、
自分の「生きる哲学」を、それぞれの方法で伝えてくださった人たちである。
その14人が、「生きる哲学」を伝えるために用いたものは何だろうか?
それは、
「コトバ」である。
「言葉」ではなく、「コトバ」
違いを簡単に言えば、
「言葉」・・・言語や文字で認識されるもの
「コトバ」・・・言語という形にとらわれない言葉
例:音楽家にとっての音。画家にとっての色。
さて、ここから、
「コトバ」の表現者たちを、その著作とともに紹介していく。
①須賀敦子
著作『ユルスナールの靴』で、須賀は、記している。
「きっちり足に会った靴さえあれば、じぶんはどこまでも歩いていけるはずだ。」と。
彼女にとって「歩く」ことと「哲学」は同義であった。
哲学とは自分にあった靴のようなものであり、
歩きながら思考することである。
「歩く」ことで世界と自分が共鳴し、
哲学に繋がっていくのである。
彼女はそうして歩くことで「コトバ」に遭遇する。
人間は「靴」を作り出すこはできないが、自分にあった「靴」を見つけることはできる。
「コトバ」とは何か、このブログを最後まで読んでいただければ分かっていただけると思う。
②舟越保武
彫刻家であり詩人でもある高村光太郎との出会いが、彼の生涯を決定づけた。
想い(詩心)が、言葉になれば詩であり、形になれば彫刻になる。
詩と彫刻、この2つは分けられるものではなく、表現手段の違いだけである。
と舟越は言う。
つまり両者ともに、コトバを通っているのだ。
日本人にとってキリスト教が母なる宗教になり得るか、を自らの人生で問い、
また、証ししようとした井上洋治神父(遠藤周作の同胞)の言葉が引用されている。
「何かを学ぶことと、何かを生きることは違う」
「前者は概念の認識だが、後者は実在の経験だからだ」
「どんなに知識を溜め込んでも人間は動かない」
「魂を揺らす出来事に遭遇した人間は、前の場所に安穏としていることができない」
ここでもやはり、このブログの冒頭に書いたように、
哲学の正しい在り方は、座学で学ぶことではなく、経験すること
だと言うことが繰り返し語られている。
舟越はこう語る。
「彫刻の仕事は、石に像を刻むことではない。石から像を彫り出さねばならない」
つまり、掘ることは、発見することであり、生きることと同義であったのだ。
生きることは創造ではなく、発見すること。
それは行動によってコトバを得ることである。
③原民喜
言葉は読まれることによって完成する。
文字に変化はないが、読まれることによって新生する。
つまり本を完成させるのは、書き手ではなく、読み手である。
広島の原子爆弾投下を経験した原民喜は、小説『夏の花』で知られている。
そこには、
原子爆弾投下後の日本の姿が、
「言葉に絶する人々の群」
という表現で、言葉では語れないことが示されている。
それでも彼は、生き残ったことで書くことが天命であるという思いの元、『夏の花』を書いた。
言葉は何かを表現できなくても、表現することができない何かの周辺を縁取ることはできた。
そうして意味を出現させるのが「コトバ」である。
彼は詩人としても知られている。
原民喜が遺した作品は、どれも亡くなった妻に向けた「手紙」だったということを、原自身が書いた記録がある。
原の「コトバ」は天に向けたメッセージだったのだ。
④孔子
この章では感情とどう付き合っていくべきかが、
『論語』を読み込むことによって書かれている。
その大半は「かなしみ」についてだ。
しかしそれは「悲しい」という感情だけのことにとどまらないということを明記しておく。
かつて「かなし」を
「悲し」の他に、
「愛し」「美し」とも書いた。
この「かなし」というのも「コトバ」を理解する上で重要なキーワードである。
他の章にも幾度となく「かなし」について触れている。
⑤志村ふくみ
染色作家として知られ、稀代の散文家、詩人でもある彼女。
この章では、五感の相互性に関して述べられている。
志村は、化学染料ではなく植物での染色に拘った。
植物から煮出した水に、繊維を沈める。
そうしたとき「手」が「耳」になると言うのだ。
「手」は色に触れ、色の音を聴く。
それは植物を育んだ土の、光の声である。
そうして志村は植物の色を「染める」のではなく、「いただく」のだと言うことを強調する。
「色彩は光の行為であり、受苦である」というゲーテの言葉。
志村はその言葉に情感を抱き、光を、色を、恩寵として受容する。
彼女はシュタイナーを敬愛していた。
シュタイナーは人間の感覚を12に分けることができると言った。
視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚、の他に、
熱感感覚、運動感覚、平衡感覚、生命感覚、言語感覚、思考感覚、自我感覚、であると。
志村と染色の関わり方を知ると、人間の感覚は、五感の領域を超えていることがわかる。
「人間の五感というものはどこかで繋がっている」
とも志村は語る。
彼女は、植物を元に「コトバ」を生み出した。
このことから、
「コトバ」は単純な五感以上の感覚で発され、また、受けられるべきであることが知れる。
⑥堀辰雄
『風立ちぬ』の作者である。
宮崎駿監督によって映画化されたことは記憶に新しい。
その題にもある「風」は何を運ぶか。
堀は同時代人の詩人リルケを敬愛した。
リルケの「レクイエム」にふれ、詩の本性ともいうべきものに出会った、とも語っている。
それは死者の国への扉を開いた。
死者は必要なとき、いつも生者のもとを訪れる。
死者となった恋人は、不可視な光を放ちながら、そばにいる。
堀辰雄の「コトバ」は、死者との協同があって、生まれたのだ。
⑦リルケ
代表作『ドゥイノの悲歌』で、彼は、大地からの轟きを「声」として認識する。
かつて自然の動きは超越のコトバであった。
たとえば雨が神の意思を表したように。
旧約聖書の預言者、孔子、老子、万葉の柿本人麻呂。
彼らは皆、語る人である前に、聴く人だった。
つまり、彼らの語りは、
何者かが彼らに託したコトバだった。
『ドゥイノの悲歌』においても、リルケは詩を書こうとしたのではなく、突如として、言葉が訪れた。
「コトバ」とは、作者が創り出すものだけでなく、待つことによって作者に到来するものでもあるのだ。
そうした自らに秘められた沈黙の言葉(コトバ)を読取る者を、自然は常に探している。
『沈黙』という代表作で知られる遠藤周作もまた、
受動的でありながら同時に創造的に『死について考える』という著作を遺している。
興味深い。
⑧神谷美恵子
「読む」とは何か?
文を読む。心を読む。空気を読む。未来を読む。
ここにもやはり五感を超えていく表現がある。
もともと「読」の字には、
「わかる」「よみとる」の意がある。
神谷の主著は『生きがいについて』であろう。
そのなかでハンセン病患者の記述がある。
彼らは点字を舌に当てて読んだ。
これを「舌読」という。
彼らは、なぜ読むのか?
それは読むことのできない友のために、覚え、語って聞かせるためであった。
神谷は、生きがいとは、
「自分がしたいと思うことと義務とが一致したとき」に生まれると述べている。
彼女が『生きがいについて』を書く契機となった出来事がある。
それはゴッホの絵を見た時であった。
ゴッホの迫るような緑に圧倒され、表現に身を捧げようと思ったのだという。
つまり、ゴッホの絵の色や線や構図(コトバ)を神谷はその時、感じたのである。
⑨ブッダ
『ブッダの真理のことば 感興のことば』のなかで、
「此岸」と「彼岸」についての定義が示されている。
「此岸」は、人間が暮らす迷いの世界。
「彼岸」は、涅槃。忘我静観の秘境。
その上でブッダは、
「人々は多いが、彼岸に達する人々は少い。他の人々はこなたの岸の上でさまよっている」
と記している。
簡単に言えば、
日々を生き抜くことは難しいが、そのなかでも「いかに生きるか」を知るべきだ、ということだ。
そしてそれを体現すると、
特定人物を示すのではない「ブッダ」になることができるのである。
(仏教では、ブッダは無数に存在しえると考える)
釈迦としてしられるブッダ(ゴータマシッダールタ)は、そのことを宣言した。
仏教とは、
「誰もが新しく生まれる」ことを説く教えなのである。
彼岸に至るには、真理を意味する「ダルマ」、
即ち、不朽の生命を照らす光を、五感を超えた認識を獲得しなければならない。
ブッダもやはり、「五感は不安定な知覚」だと、
五感のみに頼ることに警笛を鳴らしたのである。
⑩宮沢賢治
『銀河鉄道の夜』のなかに、砂の中に炎を見る場面がある。
ここでいう「炎」は「いのち」のことである。
「賢治にとって芸術は、万物の中に生ける美を見出し、その世界に明示することだった」
と若松は述べている。
美の力、美の働きによって世の中の動きを刷新しようとしたのが宮沢賢治である。
彼の詩に妹の死に触れたものが多く遺っている。
例えば『春と修羅』のなかにある「永訣の朝」がそれだ。
その詩からも、
やはり「悲し」が「愛し」であり「美し」であることが、まざまざと想い出される。
⑪フランクル
ここまで読めば、
人間が言葉を使うのではなく、「言葉の通路になる」ことがある、
ということが分かるだろう。
この章では、
石牟礼道子の『苦海浄土 わが水俣病』が検証されている。
この本は、死にゆく人たちとの「無言の交わり」によって書かれている。
言葉を失った者が発する「コトバ」。
苦しむ姿が、現実を物語る。
石牟礼は、そうした現実を目の当たりにし、コトバを「読んでいく」。
この本を書いていくことで、石牟礼は「通路」になったのだ。
受け手がいれば、行為が「コトバ」になるのである。
さて、フランクルは『夜と霧』を書いた。
ユダヤ人であるがゆえに、ナチスドイツの強制収容所に送られた実話である。
彼もまた、ユダヤ人への迫害を、彼個人のものだけでなく、全ての迫害された人たちの「コトバの通路」に立って、作品を遺した。
⑫辰巳芳子
料理研究家としても知られる辰巳は、
「食」から「いのち」とは何かを考え続けた。
著作『味覚旬月』のなかで、
彼女は「光」と「命/いのち」いう言葉を多用する。
この2つは共に、触れることのできない実在である。
食はその2つを感じる行為である。
そこにもコトバがある。食物をもたらす土について、
彼女は「土は天からの言葉」だと述べている。
つまりは、自然には天という超越者からのコトバが満ちていると言うのである。
そして彼女もまた、「待つ」ことの重要性を語る。
漬ける、煮る、など、
料理はひたすらに「待つ」ことであると。
⑬皇后
この章でのキーワードは「祈り」であろう。
阪神大震災のあと皇后美智子が被災地を訪れた。
その時、皇后の祈りによって、生者、死者ともに、光を感じた。顔を上げることができた。
『瀬音』という皇后の歌集がある。
このなかでも「かなしみ」が悲嘆にとどまらない感情として詠われている。
平和をもたらすのは「かなしみ」であるという。
それはかつて「かなし」が「美し」と書かれたように、
「美」として人々よ沈黙をもたらし、言葉を超えた交流を生む。
⑭井筒俊彦
ここまで幾度となく書かれた「コトバ」という概念を提唱したのが、井筒俊彦である。
様々な書き手を紹介したが、
書き手がコトバに身を任せて進んだ先に、ある世界が開現することが理解できただろう。
この世(あの世も含むだろうが)には様々な形のコトバが存在する。
それに気づいた人が、書き手にならなければならない。
最後に若松はこう綴っている。
「コトバは、時空間を超えてやってきた、自分に送られた手紙である」
と。
すこし考えてみてください。
あなたにも、「コトバ」、送られてきていませんか?