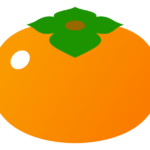七月一日。
冴がよく行くというロック喫茶に入った。普段は一人で来ると言い、僕はその姿を想像してなんだか恋しくなった。
店内には、デイル・ホーキンスの『Susie Q』が流れていた。
冴は、「ロックじゃないよ、ロックンロール」なんてキースリチャーズのような発言をして、それが僕には楽しくて、僕は早く彼になりたくなった。そしてハイボールばかりを飲んで脳に梅干しが混入したような頭痛がしてきたときには、ちょっぴり彼になっていたのかもしれないよ、今考えるとね。だって、ほらあの時僕は(ってこの「僕」は昔の彼よ)、冴にこう言ったじゃないの。
「ロックンロールの語源ってさ、セックスらしいよ」
まるで僕じゃないみたいな言葉だね。自己陶酔を促す言葉だね。無論、酒に助長してもらってね。ごぶさただね。
冴は言った。
「アラン・フリードが広めたんだよね、DJの。黒人スラングがそうやって一般に親しまれるようになったことってさ、なんか音楽のとしてのロックンロールの成り立ちそのものだよね。黒人音楽のブルースに憧れる白人っていう構図ってさ、まるでコペルニクス的転回っていうか、いやむしろ視点が溶け合ってなくなって、もうそこにはもうないけど全部あるっていうか、上も下もなくなって、地球って球体のくせにどこに立っても落ちないでしょ? その感じと一緒っていうか、非差別的で、根源的で……他にないじゃん? そんな言葉。……うまく説明できないけど……わかる?」
僕は頷いたよ。「わかるようでわからないようでわかる」たしかそんな風に答えた。渦を巻いた思考が、一つの意見としてしっかり成り立っていた。それが一として数えられた。単位を持っていた。矛盾のままでそれが立派な答え。
「頭が良いんだね」
なんて間抜けなことも言った。それでも冴は喜んでくれているように見えた。顔に出ないと言っていた冴の頬は幽かに紅潮して、目つきにいつもの鋭さは薄れていた。だたその奥にある黒い瞳の孤立無援な力強さは健在だった。
「いい目してるよね」
「ふうん。酔ってるでしょ?」
帰りに閉店間近の喫茶店に入り、一杯のコーヒーを飲んだ。
「このコーヒー一杯のために、お酒を飲む。そんな気持ちわかる?」
冴が僕を試すように訊いた。
義務としての葬儀を終えた後、私に残ったのは唯一、虚無。何もないということが何かの形を作り出して存在しているかのような。
これで私を作った人間が、二人ともいなくなった。
ははは。おもろ。だってその一つの命をなくしたのは、もう一つの命だったんだよ。そしてその事実を知っているのはこの私だけなんだよ。笑けるね。葬儀に来た父の同僚は、私に聞こえてないと思っていたのだろうか、「両親ともに自殺とは……かわいそうに……」なんて陰口をこぼしていたけどね。大人って馬鹿だね。なんにも知りやしない。いや子どもも馬鹿だよ。それで大人も馬鹿なの。つまりね、人間である限りみんな馬鹿だな、って。
私は人間になんてなりたくないよ。いやなってるんだけど。だから私は人間を動かす心ってもんを操作してやろう、って必死に心理学を学んだんだよ。人間を俯瞰して操る側に立ってみたかったんだ。それって人間の定義に従うと「神さま」ってなもんになるんだろうね。
ってことはあれれ、私って神さまなのかしら?
そんなに楽しいものではないけど、人間よりはマシね。楽しいことは楽じゃないね。
どんなに欲していたものでもいざ得てみると大概失望するね。するよね。心は満足を知らないね。或いはそれを知ってしまうことが死ぬということなのかもね。死を悟る瞬間。そんなの欲しくないね。
嫌だ嫌だ。神さまになっても、自分の心だけは思考に先行して動きやがるんだ。
私は私を常に俯瞰していたい。そのためには新しい人格が必要だった。そうして私は「おれ」にその大役を与えたんだ。
神の視点を設けて、自分を俯瞰するんだ。操り人形も、その紐を持つのも自分自身なんだ。
そう考えた瞬間、私は心が軽くなるのを感じたよ。はんぶんこ。重荷を二つに分けたんだね。
私にはきょうだいも、親もいないんだ。
その事実が己を解き放つことに抵抗を感じなかった理由なんだと思う。今になってはね。
で、私は当然のことのように大学を辞めた。お金がないってのが第一の理由だけれど、それよりも心理学部で学ぶことって別に独りで勉強しようと思えばできちゃうってことに気づいたしね。だって大学って結局は営利団体で、教育って二の次のような気がしたしね。いや教師が隠そうとしたって無駄よ、でてたもん、オーラ。見えないけど。それに友達もいないし。今まで友達なんてできたことがなかったね。もちろんご飯食べに行くぐらいの仲の子はいたけど、なんか話していてもドラマのワンシーンをお互いが演じているような気がしてさ、それって結局理想としての友達を仮装しているだけっていうか、本当じゃない感じがしたんだよ。相手は私のこと友達だなんて真面目に思ってたみたいだけど。考えてみればその頃から私は自分を俯瞰するのが好きだったのかもね。いや、好きっていっても断じて楽しいことではなかったけれど。
とかなんとか、紅葉も去りゴミ箱には腐った缶コーヒー、空気が抜けて剥げたサッカーボール、忘れたことも忘れられた麦わら帽子、目に映る全てが、呼吸を感じることのない殺風景な公園で、私はこうして出鱈目な文章を書き連ねているんですけど、そうなるに至った経緯をここに書くってのは如何でござんしょ、編集者さん、そうゆうのはあかんですか?
まあ知ったこっちゃない。
そもそものきっかけは、私の新聞投書だった。内容は割愛する。書けと言われりゃ書くかもだけど、一度世の中に出た文章をもう一度晒すというのはなんかずるい感じがして厭。その日の新聞は切り抜いて、ちゃっかりファイルに綴じちゃったりしてるんだけどね。ぺらぺらのやる気のないような紙面の片隅。そこに書き写された私の心理学と社会に対する関係の個人的な解釈を、その文体が独特、気鋭、狂喜とかなんとか適当な言い訳とともに、手紙を寄越してきたのが、今お世話になっている編集者・倉知さん。お世話になっているってのは、あくまでも金銭的な面でね。「常連なんだ」とかなんとか格好よくない格好つけながら、ご飯とか連れてってくれるし。
でもさ、こんなこと書いているだけでホントに本になるのかね。「私は不安なのよ、倉知さん」とか可愛い声で、名前も知らない雑草に話しかける体たらくよ。きゃは。
でもね、倉知さん、誤解しないで。私のタイプではないわ、あなた。
だってあなた男でしょ?
誤解しないで、読者さん。私はレズビアンではないの、決して。短絡的な思考はやめて。いつでもどこでも、よ。
きっと倉知さんは、この原稿を見て「脱線しすぎ」とおっしゃるでしょうね。でもねその意見に対する答えはもう用意しているわ、周到。
「人生なんて、脱線の連続じゃないの」