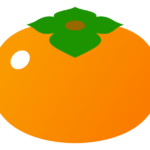「おれは父を殺したかった。だからあんな行動をしたのだし、後悔はしていない」
しかし、いまこうして目の前のベッドで無表情に静かな寝息をたてている父を見ていると、死ななくてよかったと思う。それは、安心ではない。物語がまだ途中であるということに対する興奮である。まだ私自身が生きているという感覚が、実感が、その父の小さな呼吸から生じること。その不思議。血のつながりなんかよりもっと、なにか空気中で、それはそれは科学なんかじゃ到底見つけられない何かで、私とこいつは繋がっている。おれとこいつは……。
私は彼の額に接吻する。その私と彼とをつなぐ空気中の何かとやらに存在する隙を与えないように。そうして額に唇を接しながら、いま、伝えたいことがある。
「おれの邪魔をするな」
ほのかな塩気を舌がとらえる。それは彼の味であり、塩味に似て、でも特定されるべき〝何か〟の味ではないことを、私は知っている。
その様子を見て、病室の窓の外から、たしか升口とかいう担当医(今後この医師を名前で呼んであげることはないであろうから、読者諸君はその名を覚えてあげなくてよい)が、何やら満足げに微笑んでいる。その笑みのなかに性的な高揚があることを、私は知っている。
私は思った。こいつ莫迦だな。
ばれたか? 僕はパクったのであるよ、この文章を、おほほ。あはは。ぷ! まあ、文章に限らず言葉なんてのはパクリが全てなのであって、受け売りが全てなのであって、じゃなきゃ共有できないのであって、言葉はいつも誤解を恐れずに限定する、される……。
物語は進みます。そうして僕は彼を手に入れたのです。
ところが時間がありませんので今日はこの辺で。では、後は、彼にお願いします。いいえ、お願いいたします。
低気圧の日には決まって頭痛が生じる。雨音をヘッドホンで抑えながら、彼よ僕になれと祈りながら、僕は初出勤に向かいました。緊張感のなかでは、自分の拘りなどどうでもよくなるものであります。例えばそれは喫茶店でフレッシュを拒否する僕が、缶コーヒーにミルクが入っていることを簡単に許してしまうような。
梅雨明けの報道は嘘だったのですか、と空に問うて、問うべき相手を間違えていることに気づきましたけれど、また空に問うて。問問問の繰り返し、問の向こうに答えなし。それでも僕は問いを作りだす。あらゆる哲学が陥る暗闇に迷い込む。でもね答えを見つけることよりも問いを作る方が、彼らの本来の姿なんじゃないですかね。
思っていたよりも少し早く着いてしまった僕は、祈っても祈っても僕のままであることに苛立ちを感じ、近くのコンビニで缶ビール、いいえ見栄を張りました発泡酒です、を買って一気に飲み干した。これぐらいなら顔に出ることもないし、ばれないだろうと高を括って。
わざわざきっかり十五分前になるのを待ってから十三時四十五分に裏口から入り、事務所のドアをノックする。パスタだろうか、香ばしいとはこのことかと再考させられるエビの匂いが漏れてくる。あとで知ったことによると、麺にもエビが練り込んであるらしい。余談です。そうして僕は笑顔を作る。「おはようございます」のための。人の第一印象は数秒で決まってしまう、という話をいつだか聞いたことがある。
僕の笑顔は成功したのであろうか?
アルバイトだという先輩がこうして優しく教えてくれていることからすると、及第点は超えたらしい。と決めつける。決めつけられる。ビーエイブルトゥー。
単に量が少ないからであろうか、緊張していたからだろうか、酔うことも、当然僕が彼になることもなく、僕は僕を過ごした。はい、なるほど、へえ、そうゆうことですか、ほう、すごっ、そうかあ、などと、無関心を感じさせない相槌のバリエーションに心を配りながら。
このときはまだ、冴(さえ)と出会うことなど知る由もなく。
別に綺麗でもない夕暮れ。コンビニの隣の広場で、買ったばかりの日本酒を飲んでいる。肴はハム、五枚入りで一〇八円也。すぐそこに高速道路があり、無感情的な走行音のみが聞こえてくる。それは求められた生活音。今日を終えたことに対する充足と、明日に対する不安。
ベンチに座りストローで日本酒を啜る。灌木のなかから、ひょっこり野良猫が姿を現し、目の前を通り過ぎる。その足並み、足音から知れる、ただ、今のみを暮らすことの素晴らしさ。僕は食いかけのハムをち切り、猫に向かって投げ与えた。不審そうにこちらを見るのは、なにゆえ? 僕が人間だからであろうか。詮索はよせ。猫は人間を馬鹿にしている。イコールそれは僕を。そうだろう? だって僕らは今のみを純粋に楽しむことを忘れているのだから。それもある意味、意識的に。それでも猫はハムに近づいて、匂いを嗅いでから慎重に食べ始める。
「友よ」
僕は呟く。
ハム、日本酒、ハム、猫にハム、のリフレイン。次第に僕は彼になる。彼への切り替え、それはまるで猫との同化。人間の忘却。仲間意識。
すっかり彼が僕になると、摩訶、猫の言葉が聞こえてくる。
「空腹だから食う」
猫が言う。そこに謝辞はない。僕は学ぶ。
「君ももっと食べたらどうだい? 腹が減っているんだろう。そうして手に持ちながらちびちび食べている様子は、ボクには欲望に対して恥を感じているようにしか見えないよ」
猫が言う。そこに気遣いはない。僕は学ぶ。
僕は猫に憧れる。傾倒する。
「好きだ」
と言う。その言葉に猫は躊躇いを感じ取る。そうして口の端のみで嘲笑する。される。
僕は彼になりきれていない。初めてそのことに気がつく。気づかされる。
暫し猫の存在を忘れることになる、のは本を開いたから。コンビニからこぼれる光を頼りに、文字を追うことだけに集中してゆく。
アハハ、彼になった僕がおれになってゆく……。
電話が鳴ったのは早朝で、それが今となって何時頃であったか覚えていないのは寝ぼけていたからではなく、むしろ覚醒しすぎたからである。おれはただ看護師の口調が重々しいのを感じ取り、狂喜した。
ところが、病室に入り医師から話を聞くと、その喜々が早合点であったことを知ることとなる。
看護師はいう。
「きっとお父さん、考えて考えて選んだのよ。自分で。民恵ちゃんのためを、考えてのことだと思うわ。悲しいとは思うけど、それだけは知っておいて、考えてくれたってことは」
なにを荒唐無稽なことを言っているんだこやつは。端的に言え。端的に。あんたが言わないのならおれが言うさ。
「父親は自殺しました。そうですね?」
「……きっと民恵ちゃんのこと……考えて……」
まだ言うか。おれが悲しんでいるとでも思うのか。考えているのか。あのね、看護婦。看護婦さん。確かにおれは悲しいよ。でもそれはね、あんたが考えている可愛らしい悲しみとは対称のところにある悲しみなんだなあ。
わかるかなあ、わかんないだろうなあ。
&
「え、まあドアーズとか」
他愛もない質問に冴が真剣に答える。
「渋いね」
「……Life hurts a lot more more than death. 知ってる? ジム・モリソンの言葉」
冴と出会ったのは、二日目の出勤日。彼女もまた〈へそ〉にアルバイトとして入ったばかりらしく、何かとひとまとまりで業務を教えられることが多かった。親睦が深まるのにそれほど時間が掛からなかったのはそのため、或いは、彼女の人見知りを一切しないその性格ゆえか。初めてあった日の休憩時間にはもう、傍から見たらカップルみたいよ、自分、という心地のなか、味噌煮込みキチンパスタ、とかなんだかそんな名前を店長に付けられてその日ばかりのまかないを一緒に食べた。
「タバコを吸う人?」
アイスコーヒーを飲みほして、まるでそれを合図して彼女が言う。僕は不意な質問にただ、うん、としか答えられず、そんな自分が嫌で無理して続けた言葉が「煙草吸うんや?」なんて何故か関西風になってしまって、「関西風」ってなんか料理みたいだし、そこ普通に「関西弁」でいいんじゃね? なんていちいち反省する、そんな自分もまた嫌い。
彼女は牧羊犬で、僕は羊。といった体たらくで喫煙所に到着して。
その時、僕が彼女の横顔を写真に撮りたくなったのは、筋の通った鼻の反射光と、その穴から吐き出される白い煙が綺麗な交線を描いていたからで、煙が沁みたのか細めた目つきが妙に蠱惑的であったからで、という、もし「見すぎじゃね」と問われた時の言い訳を考えながら、ただただ美しい人だと感心してしまいました、申し訳ございませんの心地。また、一歩引いて彼女を見ると、その小柄な体格にタバコというのはミスマッチで可笑しく見えるのが可笑しかったです。
というちぐはぐな本音を彼女に話したのは、それから二週間ほどが経ったある日の帰り道でした。そのころにはもう彼女の独特な強気な話し方に耐性ができて、むしろ心地よく感じられるようになっていました。たしか初めて飲みにいったのも、その帰り道でした。
確かめるべし、って紺色のノートを開いて、ほらね、間違いなくその日です。
僕はいつでも小学生の夏休みの宿題の日記のように、駄文を連ねていますので。