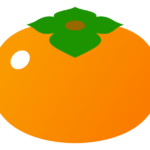それから数日間、僕は冴のことを忘れてしまおうと、気を紛らわせられそうなことをしまくった。音楽を掛けては、何時間も適当なリードギターで呼応したり、ホットコーヒーをストローで啜ったり、煙草に一本のパスタを刺して、落ちなくなった灰を眺めては「摩訶摩訶」と叫んだり、そういった類のことを延々と。
そうして僕は暇になった。暇に気づいてしまったのである。
途端に暗澹たる気分、眠れる夜が減っていった。冴に会う前の状態に戻ってしまったのである。僕は日本酒を啜りながら、未完の遺書らしき文章の続きを書こうとした。けれど、何も書くべきことは思いつかなかった。
だから、右のような文章を遺書として書き連ねることで、夜を明かした。朝になり酔いが覚めたころ、外から生活音が聞こえだすと、僕は世間と反比例するように、眠ることができた。
十九時頃に目を覚まし、僕は足の赴くままに〈有賀書店〉に向かった。着くとシャッターが閉まっていた。本屋の営業時間にさえ、僕は起きられなくなっていたのである。
僕は公衆電話を見つけ、関志絵に電話を掛けた。自分の携帯の番号を知られることは何だか気が引けたのである。
「もしもし」
か細いながらに凛とした声が答えた。
「突然電話をして申し訳御座いません。少しお尋ねしたいことがありまして。あの、有賀書店って古本屋御存知ですよね? 先ほど、あの店で本を買ったんですが、気になることが御座いまして。どうやらその本はあなたが売られたと聞いたものですから」
「ええ、私は売りましたけど……どの本ですか? たくさん売ったので」
「ええと『あなたも心理学』という……あの本はどこで、入手されたのですか? ああいえ、大変面白い本だなあと思いまして、あの本を書いた著者について知りたいと思ったのですが、著者名の記載がないので、おかしいなあと」
「あれは、うちに昔からあったんです。引っ越しついでに家にある本全て売り払ったんです。一冊十円にもなりませんでしたけれど、んふふ」
関志絵はそう言うと、照れと後悔が入り混じったような笑い声をあげた。
「あの本に著者の名前がないのは、きっと書いているのがどの自分かわからなくなっちゃったからではないかしら。簡単なことだわ。彼女はきっと人格を分化して、負担を、或いは記憶を分散させようとしていた。きっとそう。無力ね……私には想像することしか許されないの」
彼女の笑い声は、徐々に高まり、束の間の息継ぎの後、下品な哄笑が突沸した。
「あっはっははは、まだ気づかないの? 私よ、私。冴。もう付き纏わないでくれる? 私は諦めたの。もうお別れ。あの本はね、私の母が書いた本なの。あなたが最初に買った一冊。それしかないわ。こないだ関志絵が売ったなんてそんなの嘘。もう一冊も、関志絵も存在しないわ。だって出版すらされてないもの。母はね、そんなことどうでもよかったの。売るとか得るとか。だた、綺麗に本の形でとっておきたかったんだろうね。ええ。だってあれは母の遺書なのですもの。そして私がもらったのよ。間接的にね。遺書にあるべきはずの遺言らしき言葉は書かれてないけれど。まあ、人生を振り返ったんだろうね。でさ、何なの? あなたには関係ないじゃない。もう終わりなのよ。お・わ・り」
「……よくわからないな」
「そらそうよ。私だってこんなことになるなんて思っていなかったもの」
冴は言葉を詰まらせた。彼女は突然に泣きだしたようであった。
「……私は、母に会ったことがないの……いいえ、記憶の残る前には会っていたんだろうけど……私が生まれてすぐに死んでしまったから……狂って死んでしまったのよ! わかる? あなたに私の気持ちが。あの本を読んだならわかるでしょう? 私の祖父は祖母を殺した。だから私の母は、殺害者である彼女の父を殺したかったのよ。でも、彼女の父は自殺してしまった。そりゃ狂うわよ。私にはわかるわ。でも、自ら命を絶つことなんてすべきではなかったのよ。それほど天国のお母さんに会いたかったんだろうね……私だって一緒よ……お母さんに会いたい。だから私も何度も死のうとしたわ。でも怖くてできなかった。それにお母さんは、自分の生きてきた印を、名を残すためではなく、そう、印を、『あなたも心理学』という本の形でこの世に遺した。結局出版直前でその夢は途絶えてしまったみたいだけれど。私は……私がすべきなのは、お母さんがこの世にいたってことを誰かに伝えることだった。だって、きっとそれを望んでいたから。だから私はあの殆ど遺書というべき本を売って、それを読んでくれる人―お母さんのことを知ってくれる人を探した―そうして、私の役目が終わったら、お母さんの元へ行こうと思った。けど不安だったの。ちゃんと、その人がお母さんのことを知ってくれるか。だから私は傍で見守らなければ気が済まなかった。そうよ、あなたのことを。ねえ、お母さんのことわかってくれた? 可哀想な人なのよ」
「冴、落ち着け!」
「最後まで読んでくれた?」
「読んだよ。冴、落ち着けって」
「んふふ。じゃあ私の役目は終わりね……よかった」
電話はそこで切れた。
僕はもう一度掛け直した。再び冴が出ることはなかった。
今度は携帯で、鳴らした。出ない。
気に掛かることがあった。謎を解明するために、僕は〈有賀書店〉店主に電話した。
「はい」
無愛想な声が答えた。
「あんた嘘をついただろ」
「え?」
「『あなたも心理学』はこの世に一冊しかない。売りに来たなんて、嘘に決まっている」
「……知ってしまったのですね。相すみません……私はあの子がしたいようにさせてあげたかったのです」
「どうゆうことだ」
「父は母に勝てませんなあ」
「…………」
「冴は昔から内に籠った子でした。自分からやりたいことを言ったことなど一度もありません。おもちゃだって欲しがらなかった」
「どうゆうことなんです?」
僕は冷静を保つために言葉を正した。
「お気づきでしょう。私は冴の父親です。冴の初めての希望を叶えてやろうと、あの子のいいなりになっていたまでです。大丈夫です。あの子は死にやしません。いいえ、私が死なせやしません。ただ、夢を叶えることの素晴らしさを教えてあげたかったのです。まあすこし残酷な夢ではありましたが。感謝しています。ありがとう」
次に言うべき言葉を見失ったまま、電話はそこで切れた。